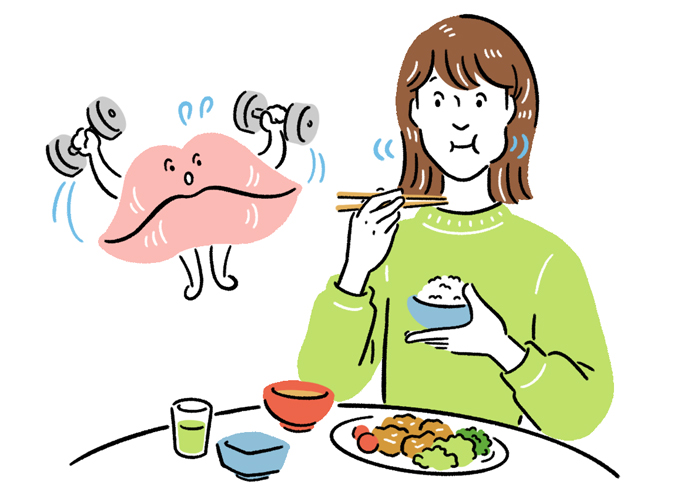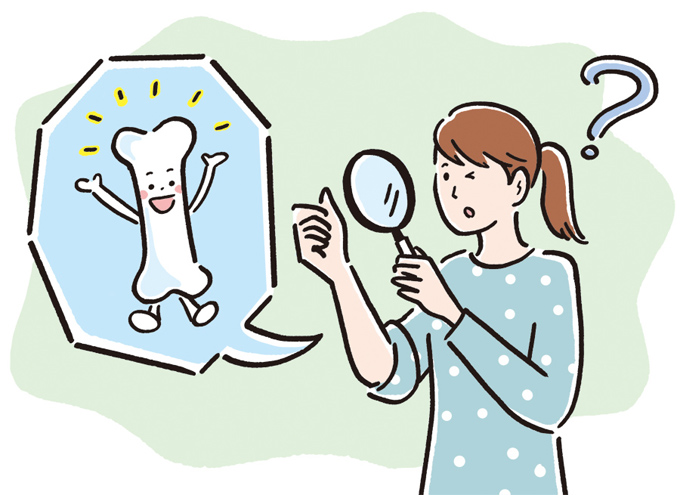よく噛んで健康づくり ②(全2回)
具体的に何回噛めばいい?「よく噛む」ために意識したいこと

「よく噛む」ってどういうこと?咀嚼の仕組みと体に及ぼす影響では、「よく噛む」ことが食べ物をより深く味わうことにつながるほか、腸や脳など体のさまざまな器官や、肌のハリといった美容面にまで影響を及ぼすことをご紹介しました。では、具体的にどのくらいよく噛んで、日頃からどんなことに気をつければ良いのでしょうか?前回に続き、和洋女子大学の柳沢幸江教授に聞きました。

「よく噛む」ってどういうこと?咀嚼の仕組みと体に及ぼす影響では、「よく噛む」ことが食べ物をより深く味わうことにつながるほか、腸や脳など体のさまざまな器官や、肌のハリといった美容面にまで影響を及ぼすことをご紹介しました。では、具体的にどのくらいよく噛んで、日頃からどんなことに気をつければ良いのでしょうか?前回に続き、和洋女子大学の柳沢幸江教授に聞きました。
「一口30回」は大事だけれど…
「よく噛む」=「一口30回噛む」ことをイメージする人も多いのではないでしょうか?確かに「一口30回は噛みましょう」と一般的によく言われますが、すべての食べ物に当てはまるわけではありません。お豆腐やプリンなどのやわらかいものを30回噛むのは現実的ではありません。噛む回数は食べ物の「噛み応え※」で異なります。
口に入れたものを咀嚼して飲み込むには、小さくなった食べ物と唾液とが混ざり合って滑らかにならないと飲み込めません。それは意識的な行為というよりも、無意識に私たちが行う「反射運動」です。そのため、噛み応えのあるものを食事に取り入れることで、自ずとよく噛む仕組みを作るなど、よく噛む工夫を意識するのが良いでしょう。
※「噛み応え」とは、嚥下(えんげ)するまでの咀嚼時の咀嚼筋活動量を反映したもので、噛む時の筋肉の力の強さと、噛む回数の両方の要素が入ります。物性的には、硬さの要素だけでなく、食べ物の弾力性や、ばらけにくさ(凝集性)が関連します。
咀嚼回数が増えるおすすめメニュー
では、具体的に「噛み応えのある」食べ物にはどんなものがあるのでしょうか?噛み応えのある食べ物としては、焼いた牛もも肉や豚ヒレ肉、生のにんじんやキャベツなどが挙げられます。野菜は全般的に噛み応えがあるものが多いのでおすすめです。

噛むときの注意点は?食事のシチュエーションも大事
年を重ねて歯も弱くなってくると、ついやわらかいものばかり食べてしまい、噛む力が低下しがちです。繰り返しになりますが、やわらかいものだけではなく毎日の食事に噛み応えがあるものを取り入れることを意識しましょう。
また、噛むときのシチュエーションも大事です。最近は「孤食」がたびたび話題になるなど、一人で食事を済ませる人も多いと思いますが、スマートフォンを片手に食事をしている人をよく見かけます。「ながら食い」は噛むことがおろそかになりやすいです。また、食べる際にあごの左右どちらかに偏って噛むと噛み合わせが悪くなって顎関節症のリスクも高まります。食事中は食べることに集中しましょう。

最後に柳沢教授に伝えたいことをうかがいました。
「前回と今回の2回にわたって『よく噛むこと』についてお話ししてきましたが、『健康のために、必ず30回は噛まなきゃ!』と義務感を抱いてしまったり、お子さんに対して何度も『よく噛んで食べなさい』と注意することが目的になってしまったりしたら、食べることや食事自体が苦痛になってしまいます。
もちろん『よく噛む』ことは大事なのですが、同時に家族や友人・知人など、誰かと一緒に食事をすることもとても大切です。例えばフレイル(高齢者が筋力や体力、認知機能など心身の活力を失い、要介護状態に近づく健康面での衰えのこと)予防の上でも、社会とつながりを持つことが大事とされています。厚生労働省(旧厚生省)等が策定した食生活指針のトップにも『食事を楽しみましょう。』と挙げられています。
また、誰かと食事を共にすると、一人でササッと食べるより時間もかかりますよね。実はそれが大事なのです。少しずつ時間をかけて食べることが満腹感にもつながりやすくなります。
もう一点、やはりご自身の歯を大事にすることはお伝えしたいです。歯の不具合はよく噛むことに悪影響を及ぼすので、定期的な歯のメンテナンスや治療も大事です。また、噛める歯を持ち続けることは、フレイル予防にもつながるので、歯も含めたお口の健康はぜひ日頃から意識してほしいです。」
このシリーズ(全2回)の他の記事を読む
- <参考書籍>
- ・小野高裕, 槻木恵一, 工藤孝文. かむ力を高めると脳も体も若返る!. マキノ出版, 2022.
<監修>
柳沢幸江
和洋女子大学教授/博士(栄養学)/管理栄養士/日本咀嚼学会、日本家政学会、日本調理科学会の理事・評議員