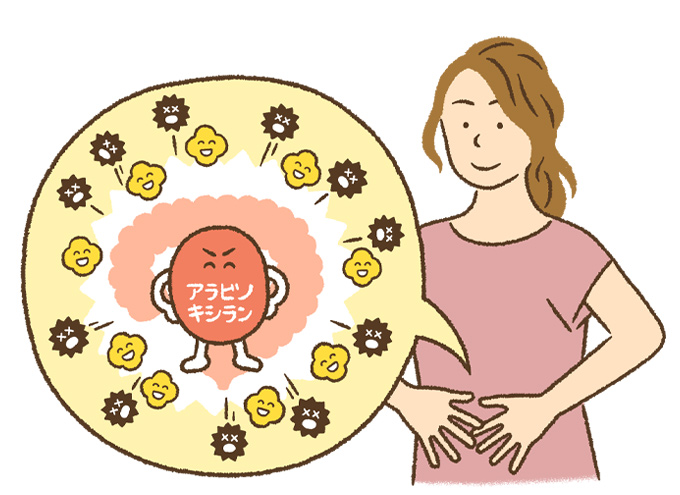イベントレポート Vol.10
「食事摂取基準の改定と食物繊維の機能性について学ぶセミナー」開催

「食事摂取基準の改定と食物繊維の機能性について学ぶセミナー」(女子栄養大学出版部主催・株式会社日清製粉グループ本社共催)を2025年2月20日(木)、女子栄養大学駒込キャンパス(東京都豊島区)にて開催しました。
本セミナーは、管理栄養士、栄養士、食の仕事に従事している方、学生などを対象に、今年改定された食事摂取基準と食物繊維の機能性について学び、理解を深めることを目的に開催しました。会場参加のほか、オンラインでも同時配信し、約400人が参加しました。

「食事摂取基準の改定と食物繊維の機能性について学ぶセミナー」(女子栄養大学出版部主催・株式会社日清製粉グループ本社共催)を2025年2月20日(木)、女子栄養大学駒込キャンパス(東京都豊島区)にて開催しました。
本セミナーは、管理栄養士、栄養士、食の仕事に従事している方、学生などを対象に、今年改定された食事摂取基準と食物繊維の機能性について学び、理解を深めることを目的に開催しました。会場参加のほか、オンラインでも同時配信し、約400人が参加しました。
第一部(前半)「日本人の食事摂取基準2025年版と食物繊維について」
第一部の前半は、女子栄養大学の上西一弘教授が、2025年4月1日から適用される「食事摂取基準2025年版」と食物繊維をテーマに講演しました。

食事摂取基準とは、日本人が何をどれだけ食べれば良いかを示したガイドラインで、健康寿命の延伸を目的として、厚生労働省が5年ごとに改定します。2025年版では「骨粗鬆症に関する指標」が新たに追加されました。

今回のテーマである食物繊維は、食事摂取基準においては炭水化物の一部として分類され、ヒトの消化酵素で消化できない「難消化性炭水化物」を「食物繊維」と定義しています。また、炭水化物全体から食物繊維を引いたものを「糖質」と呼びます。上西教授は「糖質の中でも、単糖類と二糖類を『糖類』と呼び、砂糖のような甘いものを指します。糖類の過剰摂取は肥満や糖尿病のリスクを高めるため、WHOは摂取の制限を推奨していますが、日本では2025年版で具体的な目標量は未設定のままで、今後の課題です」と指摘しました。
食事摂取基準で実際に数値が示されているのは、食物繊維と食物繊維を含む形での炭水化物ですが、炭水化物は男女ともに1日の摂取エネルギーの50~65%が目標量とされています。例えば1日に1800kcalを摂取する場合、炭水化物のエネルギーは900〜1170kcalが基準とされますが、炭水化物は1gで4kcalなので、1日に225〜293gの摂取が必要です。

一方、食物繊維の目標量について、上西教授は、生活習慣病との関連からさまざまな研究がされていることを紹介し、「この量を摂れば十分」というような明確な基準はないとしながらも、「(成人・高齢者は)少なくとも1日25gは摂取することが望ましいとされています。しかし、いきなり25gを摂るのは難しいということで、食事摂取基準2025年版では、日本人成人の摂取量の中央値の13.3gと25gの中間の値である19.2gを、目標量を算出するための参照値としました」と解説しました。

また、上西教授は、2020年版(八訂)の食品成分表改訂で導入された、食物繊維量の新しい測定法であるAOAC 2011.25法と従来のプロスキー変法では、測定している食物繊維の範囲が異なることに触れ、「食品によって食品成分表の七訂と八訂の間で食物繊維含有量が大きく異なります。例えば、玄米と精白米の比較結果が逆転したり、じゃがいもの食物繊維量が1.2gから8.9gへと大幅に増えたりするなどの影響が出ています。現在の成人女性の食物繊維目標量1日18gは旧測定法に基づいており、食事摂取基準2025年版の食物繊維の目標量は、七訂の食品成分表に基づく目標量であるため、八訂の食品成分表を用いて計算した値では低すぎる。八訂の食品成分表を使用するのであれば、より多くの食物繊維の摂取が望まれると結論づけました。
最後に「食物繊維は生活習慣病の予防に重要。まず自分の摂取量を把握し、食品成分表の測定方法の違いに注意しながら確認することが大切です」と締めくくりました。
第一部(後半)「食物繊維の機能性」
後半は、女子栄養大学の香川靖雄副学長が登壇しました。
香川副学長は「昔に比べて穀類や野菜、豆類を食べることが大幅に減り、加工食品(口当たりを良くするために食物繊維を減らしている)を食べる割合が増えたことで、食物繊維の摂取量が減少。生活習慣病の増加につながっています」と指摘。その対策として「完全食」(必要な栄養素をすべて含む食品)の研究が進められていると紹介しました。
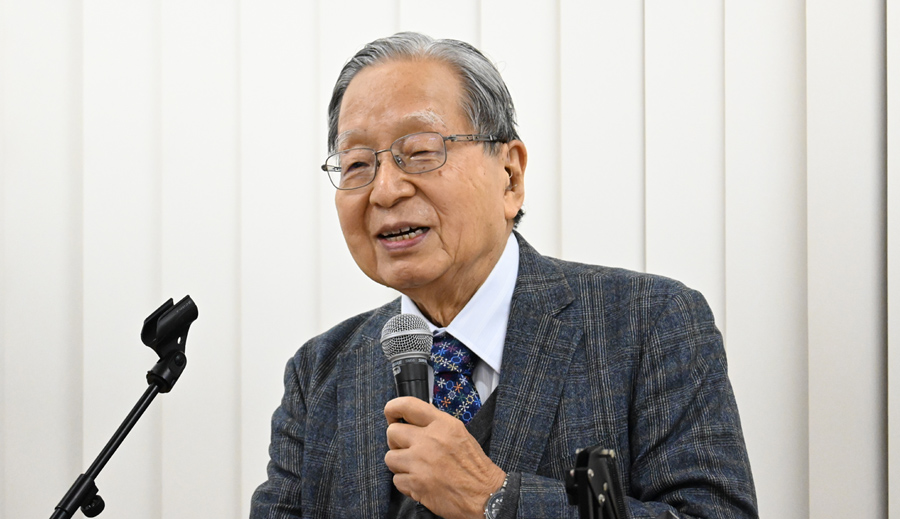
また、日本が直面する「2025年問題」にも言及。「高齢者の急増により認知症や要介護者が増え、医療・介護の負担が深刻化します。適切な栄養管理が重要であり、中でも食物繊維の摂取が健康寿命の延伸に大きく貢献します」と強調しました。
食物繊維の働きについては、「炎症を抑え、老化や生活習慣病の予防に重要。特に発酵性食物繊維は腸内細菌によって短鎖脂肪酸(酢酸、プロピオン酸、酪酸)を生成し、腸内環境を整えます。特に酪酸には、エネルギー源になったり、免疫機能を調整したり、代謝を促進したり、肥満を予防したりする働きがあります。具体的な発酵性食物繊維としては、小麦、大麦、オーツ麦に含まれるアラビノキシラン(不溶性食物繊維)やベータグルカン(可溶性食物繊維)が代表的です。さらに果物に含まれるペクチン(可溶性食物繊維)も発酵性食物繊維です。私達は最近、ペクチンが発酵して葉酸を作り、有害なホモシステインを減らすことを明らかにしました」と説明。

さらに、「発酵性食物繊維は種類によって腸内で発酵が起こる場所が異なるため、効果的に腸の機能を整えるには、特定の1種類だけでなく、さまざまな種類の食物繊維をバランス良く摂取することが望ましい」と述べました。最後に「日本人の食物繊維摂取量は不足しています。食物繊維の種類と役割を理解し、日々の食事で意識的に摂取することが重要です」と話し、講演を終えました。

講演後にはセミナーの参加者から「人によって腸内細菌叢に違いがあり、抗生物質の服用によっても腸内細菌叢が変化することが考えられますが、それぞれに合わせた食物繊維の適切な摂り方があるのでしょうか?」という質問が寄せられました。
香川副学長は「抗生物質を使った後は、腸内環境を整えるためにプロバイオティクスとプレバイオティクスの両方を意識して摂ることが大切です。プロバイオティクスとは、善玉菌そのものを含む食品のことで、ヨーグルトやキムチなどの発酵食品が代表的です。一方、プレバイオティクスは、腸内の善玉菌を育てるエサになる成分で、水溶性食物繊維が豊富なオートミール、バナナ、海藻類などがこれにあたります。これらをバランス良く取り入れることで、抗生物質によって乱れた腸内細菌のバランスを回復することができます」と回答しました。
第二部「高食物繊維がとれる献立」
第二部では、管理栄養士・料理研究家の牧野直子先生が高食物繊維レシピを紹介。会場では、ひよこ豆のフムスを塗ったパニーニ(食物繊維含有量は11.5g)が振る舞われました。
「基本となるのは、栄養バランスの取れた食事」と牧野先生。「炭水化物は糖質と食物繊維を合わせたものですが、『糖質オフ』ブームの影響で、炭水化物=糖質と誤解し、極端に制限する人が増えています。炭水化物を減らすと、結果として食物繊維の摂取量も減ってしまう」と警鐘を鳴らしました。

そして、「主食は、玄米など精製度の低いものや雑穀米、白米に混ぜても違和感がなく、水溶性食物繊維を多く含むもち麦などを取り入れると良いでしょう。パンなら全粒粉のパンやライ麦パン、パスタなら全粒粉入りのものを選ぶことで食物繊維を増やせます。主菜は肉や魚だけでなく、大豆製品(納豆・豆腐など)を組み合わせ、炒め物や煮物に野菜やきのこ類を加えるのがおすすめです。副菜は野菜や海藻類を積極的に取り入れましょう。ブロッコリーやほうれん草はゆでて冷蔵保存すると便利です。カットわかめや、味付もずく、めかぶも活用できます。間食には、果物やドライフルーツ、ナッツ類、和菓子(あんこ入り)を選ぶと食物繊維を補えます」と毎日の食事で食物繊維をうまく摂るための工夫についてアドバイスしました。






セミナーに参加された方々は、メモを取るなど講師の話に熱心に聞き入っていました。ご参加いただいたみなさん、ありがとうございました。

女子栄養大学 副学長
香川靖雄

女子栄養大学 教授
上西一弘

管理栄養士・料理研究家
牧野直子